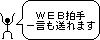
ステラは掃除と後片付けというものが一番好きだった。
シンと二人の時、唯一「任せて」といえること。一人で、ちゃんとできることなのだ。そして、ミネルバの皆が来てくれたこの日だってそ
うだ。料理はできないが、これはできる。
温かくて美味しかった料理のお礼は、あとは任せてと言うことで返したかった。
そう思って、ステラは誰より早く立ち上がった。
「・・・・・・あの」
ステラの声にタリアが顔を上げる。テーブルの上の料理はほぼ綺麗になくなり、室内では大人たちが杯を傾け合っていた。
「みんな、座っててほしい」
「ステラ?いいのよ、わたしとやりましょう」
アーサーに自分のグラスを渡すと、タリアはソファから立とうとした。すぐにステラがその肩を両腕で留める。
「いい、おねがい。ここにいて」
懇願の眼差しでステラは必死にタリアを見つめた。隣でアーサーが苦笑するのが見えるが、ステラは退くつもりはなかった。
「艦長、お願いしたら?」
返事ができずにいるタリアにヨウランが言う。必死なステラを見ていると、なんだか兄貴になった気分だとヴィーノも呟く。
困ったように笑ったが、タリアはもう一度ソファに座り直すとアーサーからグラスを受け取った。
「任せるわ、ステラ。あとで、ルナマリアの買ってきてくれたデザート食べましょうね」
「うん」
ぱあっとステラは笑顔になり、跳ねるような軽い足取りでテーブルへ向かった。早速、トレンチを出してきて片付けようとしていた。
その背中は懸命で、タリアは微笑まずにいられなかった。
まるで、子供が親にいい所を見せたいとせがむ様な・・・・・・任せてもらえて認めてもらえたと喜ぶような、そんな背中に。
「艦長、ちょっといいですか?」
まだステラの後姿に気をとられていたタリアだったが、向こうからやってきたシンに気づき振り返った。レイやルナマリアも一緒かと思えば
そうではなかった。
「ええ。シン、どうしたの。改まって」
返事をして少し詰めて自分の隣の席を促した。向かいのソファに座るヴィーノとヨウランが姿勢を正すのが見え、何故か緊張しているように
感じた。座ったシンの表情も硬い。
訝しげにタリアは首を傾け、アーサーの方を見やる。
「何か悪さでも隠してたの?」
「え?自分は存じていませんが・・・・・・」
アーサーは焦ってすぐに答えた。それでも青年たちは硬いままだった。
「艦長、頼みがあります」
ゆっくりと息を吸ってから、シンは真っ直ぐにこちらを見て言った。
意思のある瞳。揺るぎない思いを感じさせる。戦時中はその瞳を行き過ぎた狂気に感じたこともあったが、今の彼は深い慈悲を湛えた男らし
いものへと成長していた。
我が子のように、嬉しく思う。戦が終わり、こうして生きて部下の成長が見れることは一番の至福だった。
「なに」
「・・・・・・俺、結婚したいんです。ステラと」
目を見開いたタリアは、思わず声が出なかった。
噂では、耳に入っていたがこんなふうにシンが言ってくれるとは思っても見なかったのだ。
「それで、俺には両親がいないし、ステラにもいないので・・・・・・艦長に、」
そこまで言って、シンは少しだけ視線を外した。膝の上で握った両の拳に力が篭っている。その様子を、そこにいたヨウラン、ヴィーノ、アー
サーまでもが息を呑んで、拳を握った。
「タリア艦長に、認めてほしいんです。俺たちの結婚」
顔を上げて、勢いよく言ったシンの声が室内に伝わった。
澱みない気持ちが言葉すべてに沁みていて、聞くものすべての胸に届いた。飾らないシンらしい頼みごとだった。
「艦長・・・・・・?」
まったく何も言う気配のないタリアに、掠れた声でシンはおずおずと聞いた。
「・・・・・・シン・アスカ」
「は、い」
「そう・・・・・・シン・・・・・・」
タリアは微笑んだ。ゆっくりと、愛しそうに。
戦をして良かったことなんてなにもない。なにもないのだと思う。しかし、思わずにいられない。間違いばかりではなかったのだと。こうして
部下たちに出会えたことは、運命であったのだと。
本心を言えば、ずっとシンのことは心配であった。戦後のザフトでの任務の中も危うい雰囲気があるときがあったのを何度か見たことがある。
よく言えば真っ直ぐで前向きなのだが、悪く言えば思い込みと周囲が見えなくなるのがシンである。タリアにとっては、他のクルーと違った意味
で彼がいくら昇進したとしても気に掛かる部下だった。
それだけに、いくらか厳しい態度で接してきたのは確かだ。彼を間違った方向へ行かせたくない一心だったが、シンにしてみればお節介であっ
て、鬱陶しい上司であるに違いないと思っていた。ステラのことだってそうである。あの時、本国にステラを送ると決めたのもタリアだ。
こうして、ステラに出会い話す様になって、シンに対する気持ちは複雑になる一方だった。自分はミネルバの艦長として間違えた選択はしてい
ない。連合の兵士であったステラをそうすることは仕方のないことだった。だが、人としてと問われれば、返す言葉を今は持っていなかった。
近くにはなれない、そう勝手に思っていた大事な部下は、迷いもせずにタリアを選んでいた。
「ありがとう、光栄だわ。本当に、おめでとう」
シンの肩を抱き寄せ、頭を撫でてやる。そっと、何度も。
おめでとう、という言葉よりも本当は、頑張ったねと言ってあげたかった。ここまで、本当に多くの悲しみと苦難を受け止めてきた青年。甘え
たい年頃だったはずだ。わかっていても、素直になれず体当たりしてしまう年頃だったはず。なのに、吐き出すことなく彼はもう大人になってし
まったのだ。
「認めてくださるんですか?」
腕の中で、シンは微かな声で聞いた。抱きしめた肩は僅かに震えてる。
「ええ。当たり前でしょう」
なんて幸福なことだろう。
彼らに、そういえることが。
「よかった・・・・・・は、はは・・・・・・正直、びびってたんで」
「そうね?貴方はいつも私を怒らせてばかりですもの。不安だったのはわかるわ」
タリアは腕を離さずに、そのまま震える背を摩ってやった。
「こんな息子じゃあ、ステラを任せられないって言われてもおかしくないかもしれないしねえ」
シンの肩が一度大きく動いて、耐えるように動かなくなった。タリアは、抱きしめた腕の中の青年の確かな存在感に安心した。
「おかしいわね・・・・・・もう二年も経つのに、今貴方が本当に生きていてくれてよかったと。そう改めて思う」
そう言って、タリアは包むようにシンの顔に触れた。
「ありがとう。シン」
タリアを映しこむ朱色の瞳が、ゆらゆらと揺れて透明な涙が広がって流れ落ちた。零れても零れても、とめどなくタリアの手を伝った。
もう、何も言葉は必要ない。
こうして分かち合える気持ちがあることを、心から感謝した。
あの時、生きる選択をできたことを。
我ながら、本当に良い手際で出来ていると思う。
ステラは嬉しくなって、自分の顔が映りこむほど磨いた皿を手にとって笑顔になった。
これなら、喜んでもらえるだろうか。
そこまで考えて、ステラは息を吐いた。
シン、泣いてた。
声がしたから、部屋をのぞきにいったらタリアの胸でシンが泣いていた。
訳は読めなかったが、悲しくて泣いているのとは違うようだった。
でも、気づいたことがある。
いつもは、ステラがああしてシンの胸を借りる。シンがそうすることはない。でも、タリアの胸を借りて泣くシンの姿はとても小さく
てステラの知っているシンとは違った。
タリア。
なんだか、シンとはまた少し違う温かい感じがする。こちらを見て微笑まれると、胸がくすぐったくて何を話せばいいか迷ってしまう。
見つめられると、理由なく温度があがった。
皆も同じようだった。タリアを囲むミネルバクルーは皆揃って嬉しそうに彼女の周りに集まっていた。それが羨ましくて、すぐにその輪
に入っていけない自分に悲しくなった。だからといって、なぜ行けないのかも行きたいのかも自覚できていないために、ステラは戸惑って
いるばかりでろくに話も出来ず仕舞いである。
どうしてだろう。
どうしても、あそこへ行けない。
シンはいつでも、おいでと手を差し伸べてくれる。
みんな、優しい。
でもそれはステラにではなく、シンにだと思うのだ。シンは皆に必要とされている。いつでも、誰もが彼の隣にいると楽しそうだ。
ステラだけのシンではないことは、わかっている。
ステラだけ、見てほしいの?
そうではないと思った。
みんなといるシンを見ているのもとても好きだ。こちらの心が温まるほど、仲間といると良く笑う。ステラといる時はあんなふうには笑わ
ない。
いつでも、ステラを待っていてくれる。
あんなふうに、じゃれ合ったり、言い合いしたり、大声で笑いあったり、しない。
今日、帰ろうと言ったらシンはどうしてか泣きそうな顔をした。
何がシンにそんな顔をさせたのだろう。
もやもやする。わからないことが、苦しい。
一体、ステラにはシンに何が出来るんだろう。
どうすればあんなふうになれるのだろう。
「シン・・・・・・」
口唇に乗せた大好きな名前。
言って、指で触れてみる。そこに何があるわけでもないが、いつもとは違う苦い味がする気がした。
「どうした。シンなら、みんなといるぞ」
残った皿を手にレイはキッチン入ってきた。声を聞きとめて問うた。
「・・・・・・おつきさま」
「ん?」
洗物を終えているのに皿を見つめたまま止まっているステラにレイは首を傾げたが、振り返ったステラはぼうっとした瞳でそう
呟いた。
「あなたは、おつきさま」
無表情だったが、ステラは僅かに目じりを綻ばせた。
「俺のことか?金髪だからか?」
「きれい」
淡々と呟きを重ねると、ステラは背を向けた。もう洗物は手元になさそうだったが、蛇口をひねってまたぼうっと動かなくなる。
レイは近づいて、手にある食器を流しに置いた。
「シン、呼ぶか?寂しいのなら」
「い、や」
ステラは急にレイを見て、激しく顔を横に振った。
「さみしく、ない。ステラ、だいじょうぶ」
「やっぱり何かあるんだろう?待っていろ」
自覚はないようだが、ステラの瞳は涙が滲み、今にも泣き出しそうだった。
シンを呼ぼうと動きかけたレイの前をステラは勢いよく横切って、行く手を塞いだ。
「だめ」
必死に顔を振って、両腕を広げるステラにレイは驚いて黙った。何も言わないレイにステラは口唇を真一文字に結んで睨んだ。
「どうした」
「・・・・・・だめ。シン、迷惑。ステラ、一人だいじょうぶ」
睨んだ先のレイはまた驚いたように瞬いたようだった。しかしステラは退けない。あんなにいつでも一緒にいたいシン。でも今は
会いたくなかった。来てほしくない。
みんなといるのだから。
「あいつも悪いが・・・・・・君もだな。ステラ」
「だめ。わかる、ステラ。じゃま」
おかしなことを言っているつもりなんてなかった。ステラにとって、今レイにシンの元に行かれるのだけは避けたかった。こんな
おかしな気持ち知られたくない。こんな自分を見られたくない。
「ステラ、あたまわるい。わからないの」
ありったけの記憶力を振り絞って、言葉を探した。抱えた意味不明な気持ちを説明できるような、言葉を。
目の前のレイは何の表情も浮かべずに、じっとこちらを見つめているようだ。ずっと綺麗だなと思っていたお月様みたいな人。シ
ンの仲間。大事な人。こんなふうにお喋りしたかったのではないのに。
「ステラ、シンが君を邪魔に思うわけないだろう?それに、あいつは自分の知らないところで君が悲しんでいると知ったら傷つくん
じゃないか?」
「・・・・・・いま、みんないる。だいじょうぶ。ステラ、かなしい、ない」
「君の言う邪魔というのは、みんなといる時間を邪魔したくないということか?」
「おねがい。シン、よばないで」
ステラはレイの腕を掴んだ。揺さぶって、お願いと繰り返す。
「わかった。呼ばない。代わりにルナマリアを呼んで、三人で散歩にでも出ないか」
レイはそう言うと、そっと握ってきたステラの手に触れた。弾かれたようにステラはその温かさに顔を上げた。
シンが一緒でないのに?
「行こう」
返事を待たず、レイはそのままステラの手を握って歩き出した。
「もう、すっかりやんだわねえ」
ルナマリアは腕を上げて伸びをすると、見上げた月に向かって言った。
まだ湿った砂に足を取られながら、ステラはルナの後ろを歩いていた。少し湿気が多いが気持ちのいい風が小波と共に海からやってく
る。纏わりつく髪を押さえながらステラは、横にいるレイを見上げた。
ぼんやりと月明かりが砂浜を照らし、きらきらと光っていた。
「ルナマリア、あまり近づくと濡れるぞ」
「わかってるって。でも、あ!見て、見て!ステラ」
振り返らずに返事したルナは波打ち際を指差して、ステラを呼んだ。
苦笑したレイが戸惑うステラの背を押して、頷く。
「・・・・・・ルナ?」
「ほら、見て!」
おずおずとルナの所まで行き、指された方向を見た。ほら、とルナの寄せてきた距離にどきどきした。
「・・・・・・あ」
「かわいいねえ」
波から、ひょっこり顔を出して上がってくるものがあった。ひょこひょこと歩き、時に強い波に戻されたりしながら彼らはのんびり砂浜
を目指していた。
「亀よ、カメ。見たことある?」
「ない」
暗いのでステラにはただの黒い丸い物体が動いているように見えたが、よく見ると甲羅を背負った姿をした生物のようだった。出たり引っ
込んだりする首が、なんとも愛らしい。
亀たちは、一列になって砂浜にあがってきて立ち止まった。
「いち、にい、さん、しい、ご・・・・・・家族?」
「うん、そうかも。あの一番大きな甲羅がお父さんかしら?」
「おとう、さん」
ステラはじっと息も忘れて亀を見つめた。
寄り添うように、みんなでじっとしている。それはとても幸せそうに見えた。
家族。
お父さん、お母さん。
これがそうなのかな。これが、家族。一緒にいるということ。
ステラの入っていけない、輪。
「ルナ」
「ん?なに」
いつも変わらないルナ。
ステラより綺麗で、頼りがいがあって、皆に必要とされている。見つめていると、いつも嬉しくなった。綺麗で強いルナが好きだ。でも、
どうしてか今はその気持ちが湧いてこなかった。
もやもやする。
「シン、すき?」
「・・・・・・好きよ、あいつバカだけど。そういう仕方ないところが」
もやもやする。
「でも、それはステラがあいつに好きっていうのとまた違うわよ。私、あいつより可愛いステラのが好きだし」
どうしよう、もやもやする。
「ま、あいつはステラ以外見えてないしね。聞いたわよ、プロポーズされたって」
胸が、おかしくなりそう。
「ステラ?」
ステラは走り込んで、亀たちのところに行った。
肩でぜいぜい息をしながら、輪になって休憩しているのを睨みつけてとまる。
次の瞬間には思い切り砂浜に膝を折って突っ込んでいた。
輪を散らすように砂浜を手で散らす。
後ろで止めるルナの声が聞こえたが、とまれない。
亀の親子たちは驚いて、散り散りに離れていく。
「うっう、ああ、ああああぅ」
掻き散らした砂浜の上で、ステラは蹲って声をあげた。
苦しい、苦しい嗚咽のような声。
こわい。苦しい。
知らない。こんな気持ち、知らない。
泣くと口の中がざりざりしたが、抑えられなかった。急に湧いて起こった衝動に、どうしようもなかった。
「ステラ、どうしたの・・・・・・」
「ルナマリア」
近づこうとしたルナの肩をレイは止めた。
背を丸め、震えながらステラは泣いていた。駆け寄らずにはいられないその姿にルナはレイの手をどけた。
「だって!」
「ステラはきっと、嫉妬してる。でも、それが初めてのことで理解できてない」
「嫉妬?」
「ああ。シンをとられるのではないか?シンは皆といる方がいいのではないか・・・・・・シンには足手まといのステラより、強くて綺麗なルナ
の方がふさわしいのではないか」
そしてきっと、一緒にいることが当たり前のように自然な亀の親子に嫉妬したのだろう。
知らず、気持ちのどこかで「ひとり」であれば、傷つかないことを認識しているのかもしれない。ずっと、そうして過ごしてきたのであ
れば彼女にとって、家族や仲間といった言葉は理解しがたいものなのは当たり前だろう。
知らないのであれば、傷つかない。知る前に消せば、なかったことにすれば、気にすることもない。そうすれば、彼女たちエクステンデッ
トは、鬼神のように戦うことができるのだから。
苦い思いで、ルナと二人、いつまでも嗚咽に震えるステラの消えそうな背を見つめた。
「シンはシンで、あの子を失いたくない一心で錘になりたくないと言っていた」
あいつらしい。ルナは言葉にしないが嘆息した。
「ステラはステラで、初めて知った感情に戸惑い、シンにとっての幸せを考えたとき自分という場所では相応しくないのではと思っている」
だいじょうぶ、じゃま、と繰り返したステラが脳裏を過ぎる。
体の成長も、心の成長も、留められ、縛られた少女は、全身で進もうとしていた。その先を知りたくて。でも、弱い心が怖いと叫ぶ。レイ
には痛いほど理解できた。
なんて、不完全な存在。
なんて、簡単にいかない自分。
「ステラ、立て」
レイはその場で、静かな砂浜に響く強い声で言った。
隣でルナが驚いて瞬いている。
「立つんだ、自分で」
ステラの丸まった背は動かない。
「ステラ、またシンがくるまでそうしているのか?シンが手を差し伸べるのを待つのか?」
びくっとその背が動く。
シン、という言葉にステラは留めていた嗚咽を漏らした。
「シ・・・・・・だ、め。うう、きらい、ならない・・・で」
「だったら、自分で立つんだ。ステラ、俺たちが教えてやるから。その気持ちを」
「レイ」
ルナはもう一度瞬いて、レイを見つめた。こんなレイ、見たことがない。いつも冷静で、他人のことにはあくまで一線をおいて付き合う。
アカデミーの頃から、相談には乗るが相談はしない。答えを持っていても、それは告げない。それなのに。
「シン・・・・・・」
「そうだ。必要とされたい思うなら、勇気を出せ」
名を呼ぶと、心に灯がともる。
シン。
いつでも優しいシン。大好きなシン。
知りたい。
怖いけれど、知りたい。
シンを失わずにすむのなら。
「う・・・・・・」
髪や頬からずり落ちる砂を感じながら、ステラは顔を上げた。震える腕をなんとか抱えて、上半身を砂から起こした。
「あ、か・・・め・・・・・・」
ゆっくり動かした視線の先で、亀の親子たちがまた輪を作って寄り添っていた。先程よりも近く守りあうように。
そうか。
わたしが邪魔したって、なくならないものなのか。
タリアの側に出来る輪。
シンの側にある輪。
亀さんたちの輪。
その輪にステラも入りたい。
あの、温かそうな場所に入ってみたい。
「かめ、さ」
膝を引きずって、ステラは亀たちの輪に近づいた。ゆっくり、怖がらせないように。
「ごめん、ね」
まだ震えの止まらない手を伸ばして、五つ集まって動かない亀の甲羅に触れた。水面を撫でるようにそっと。
大きなお父さんの亀がうごうごと動いて、ひょっこりステラのほうに顔を出した。
「おとう、さん。ごめんね」
初めて間近に見た亀の目は大きくて丸く、硝子玉のようだった。コニアの作る七色の硝子に似ていた。
「う、う?」
お父さんの亀をじっと見つめていたら、知らない間に一番小さな子供の亀が砂浜についた手に登ってきていた。手に柔らかい感触がする。
小さなかわいい爪がステラの手から落ちまいと、踏ん張っていた。
「・・・・・・ふ、ふふ、かわい」
酷いことをしたのに。怖がりもせず、そこにいた。
ステラを拒むことなく、そこに。
「ありがとう」
ステラは落とさないように手のひらに小亀をのせて、呟いた。返事はないが、上下に動いた首が頷いているようにステラには映る。ひどく
幸せな気持ちがした。
シンがおいでと、手を広げてくれた時のような、そんな幸せ。
「またね」
小亀を輪に戻してやって、ステラは砂だらけでのろのろと立ち上がった。雨上がりの砂浜に突っ込んだものだから、顔も着ていた白いコー
トも砂だらけでぐしゃぐしゃである。
ルナとメイリンがせっかくお風呂に入れてくれたのに、大いに台無し状態だった。
「・・・・・・ステラ!」
頼りない足取りでレイとルナのほうへ歩いたステラを、ルナが待ちきれずに駆け寄って抱きしめた。
「ルナ、よごれ」
「いいの。もう、心配させないで」
ルナの香りがする。抱きしめられた強さも、吸い込めばする香りも、大好きだった。
「あんた、バカね。シンとそっくり」
「ごめん、なさい」
「いい?私たちはステラといるのよ。シンといるステラじゃない」
何といえばいいのか言葉が見つからなくて、ステラは黙った。ルナの言ったことはどういう意味だろう。
シンといるステラじゃない。
シンといなくても、ステラといてくれるってこと?
「ステラ、ルナのこと。すき。ルナは?」
抱きしめた腕を緩めて、ルナはステラの顔を見て笑顔になる。
「好きよ。当たり前じゃない」
「!」
ルナの笑顔はきらきらしていて、眩しいほどだった。なのに、彼女の瞳から次いで大粒の涙が零れ落ちた。
「る、るな・・・・・・」
「あれ?あれ、おかしいな。なんで涙がでるんだろ」
困ったステラが後ろのレイを振り返ったが、レイは微笑んで顔を振った。
「染みたんだろ、いろいろな」
言って、またレイは笑った。ルナと同じ笑顔だった。
「意味深に言わないでよ、レイ」
「天下のルナマリアも、ステラには勝てないな」
「う」
言葉に詰まって、ルナは溜息をついた。わかってしまった、シンがなぜあんなにぞっこんなのか。
そして、そのお陰で凝り固まっていた気持ちが溶けてゆくようだった。この子はまだ多くの意味で子供だ。手放すことも、戻ってくること
もこれから教えてやらねばなないのだ。
シンと戦場で出会い、漸く目覚めたのだ。ステラという少女は。
そう思うと、少なかれシンを奪われたような気がしていた自分の気持ちや、幸せそうな二人を複雑な思いで見つめていた気持ちが緩やかに
萎えていく。
ルナ自身も、出会うべき人であったのだ。
みんな、そうであるべき繋がりだったのだと思うと、やはり涙が止まらなかった。
「ステラにかかると皆、泣き虫になるわね」
「?」
浮かべた涙をそのままにルナはステラの頭を撫でた。その手はやっぱり温かくて、優しくてステラは目を伏せる。どこかで、感じたことの
ある温度。シンのくれるのとまた違った温かさ。
はっきりとは思い出せないままだったが、この温度の名を知っている。
そう、ネオ。ネオだ。
だからステラもそうしたい。もらった温かさを返すことが出来るようになりたい。
「・・・・・・つき」
ルナの涙をステラは拭い、少し開いた距離を埋めるように体を寄せた。
「にてるの。おつきさまにレイ・・・・・・ルナも」
「え?レイと、あたし?」
間近にある金の天使の輪にルナは手櫛しを入れてやり、レイを見やった。
「レイはなんとなくわかるけど・・・・・・あたし?」
「ルナ、にてる」
そういって、ステラは頭上の月を指差す。
見上げた月はもうぼんやりしていなかった。
くっきりと黄色くひかり、澄んだ空にぽっかり浮かぶ。手を伸ばすとつかめそうなのに、手が届かない。
でも、ずっとつかず離れず側にいる。
「・・・・・・俺も、ステラにはかなわないな」
二人には聞こえないように、そっとレイは呟いた。
小波が、寄せては返す。
決して同じようには繰り返さないその音が、飽きずに月に見惚れるステラには音楽に聞こえた。
やむことのない、いつでもここにくれば聞くことのできる音楽。
走っても、遅くても、笑っても、泣いても、どこからでも見える月。
変わらない音楽。
あんなにもやもやしていた気持ちは、月にかかる霧と共に綺麗にどこかへ消えていた。
部屋はすっかり片付けられて、あんなに人で溢れて狭かったように感じた室内はやけに広く感じられた。
シンはソファを元の位置に戻し、時計に目をやった。
もう日付が変わってしまった。
小さく、ひとつ息を吐いて、シンはテーブルの上に置いてある宝石みたいなチョコレートたちを見やった。
細かいデザインの施されてたチョコレートの粒は、お行儀よくステラお気に入りの花の形をした皿に並んでいる。シンはそれらをお店の
ショーケースで見たことがあった。
思い出して苦笑する。
嫌いではないがチョコレートに高級だの、お洒落な名前だの、シンには理解できず、付き合わされては嫌な顔を隠さなかったものだ。
きっと、ステラも気に入るだろうと買ってきてくれたものだろう。
ルナらしい心遣いにシンは、目を伏せた。
皆が帰ろうという頃に、ステラはレイとルナに連れられて散歩から帰ってきた。
それはもう泥だらけで。
結局、時間がなくてデザートは皆で食べることができず、こうしてテーブルに並んでいるのだ。
そして、今は。
シンがカーテンを閉めようと窓際に歩み寄った時、部屋の扉がそっと開いた。
「シン」
ひょっこり顔を出したステラは、入ってくるなりシンの元へ駆け寄ってきた。
「ステラ。ちゃんと髪、乾かさないとだめだって。あ、寒いんだからちゃんとパジャマ着なきゃ」
「シン」
嬉しそうにシンを見て笑うステラだが、本当に風邪をひきそうな格好だった。慌てて、シンはステラの手からタオルを取って濡れた髪を
拭いてやる。
「どうして、ワンピースなんて出してきたんだ?もう寝るよ」
ステラお気に入りのラクスにもらったワンピース。淡いピンク色をしたふんわりしたもので、それを着ていると妖精のように見えた。
妖精って。
シンは一人でステラの小さな頭を拭きながら、笑った。
「ん。今から、こくはくするから」
「へえ・・・・・・え?」
「ここ、座って」
ステラは拭かれているタオルを取って椅子にかけると、シンの腕を引いてソファに連れて行く。
「はい」
「え、あの。ステラ?」
シンを座らせて、ステラは真剣な顔で頷くと、自分も隣に正座した。
まだ乾ききっていない髪が頬にかかっていたので、シンは思わず情景反射で手を伸ばし直そうとした。
「シン!」
「はい!」
驚いて伸ばしかけた手を止め、シンは座りなおす。それぐらい気合の入った呼び方だった。
「あのね、」
言いかけてステラは、はっと息を呑む。待てという意味なのかシンの前に両手を出してとめると、後ろを向いて自分で髪を整えている。
何事か小さな声でぶつぶつ言って、もう一度こちらに向き直った。
少し薄い桜色の口唇が、何度か空回りしてから、漸く目的の言葉を紡ぎだした。
「きょう、レイとルナとお友達になりました」
シンは瞬いて、きょとんとした。ステラはそれでも、めげずに深呼吸して続ける。
「シン、と、ステラ、はべつべつのひとで、ステラがすきなように、みんなもシン、すき。シンのこと、すきなように、ステラのこともレイ
やルナ、あと、みんなも、すきでいてくれる」
一生懸命、ひとつひとつステラは話した。伝わってほしい思いが大きくて、つい体は前のめりになる。シンは黙って、朱色の瞳を真っ直ぐ
こちらに向けて聞いてくれていた。
伝えたい。
私は、貴方が好きなのだと。
貴方だから、一緒にいたいのだと。
そして、いつか、私とシンの輪が作りたいのだと。
「でも、わかった。ステラ、みんなのすきと、シンのすき、違う」
言葉にする度に息が苦しい。なんだろう。
さっき物凄くもやもやした時も、心臓が壊れるのではと思ったが、今も何故か早鐘のように鼓動が早くなった。
「ステラのすき、シンだけ。シンのこと、ほしい。シンが、ほしい」
初めて知った独占欲。
初めて口にした、ほしいもの。
寝れば、すぐに嫌なことも怖いこともなかったみたいに忘れたのに、今では寝ても覚めても、忘れられない。貴方のことが離れない。
シン、なんていえばいいの。
側にいるのに。
側にいるのに、もっと側にいてほしいとき。
なんていえばいいの。
「・・・・・・こくはく、です」
言い切って、長い長い沈黙のあと、漸くステラは呟いた。
息が苦しくて、うまく呼吸ができない。シンの顔が見たいのについ俯いてしまった。そうなると、なんだか上げづらくなってしまい、本当
にシンの顔が見れなかくなった。
どうして何も言ってくれないのだろう。
聞こえてくるのは、時計が秒針を刻む音だけで、それ以外は何もなかった。
「君は」
本当に長い沈黙のあと、シンの声がぽつりと響いた。
思わず、ステラは勢いよく顔を上げる。
「・・・・・・シン」
息が出来ない。
シン。そこにいるのに。すぐ側にいる大好きな人。
ステラの瞳に映ったシンは、ステラと同じように息を殺してそこでじっと何かに耐えていた。朱い瞳が苦しそうに細められる。
「どうしよう」
大好きな声が、呻くようにそれだけ呟いた。
「どうしよう、俺・・・・・・」
続けて、シンはステラの方へ近づいて自分の額をステラのそれに優しく合わせて、深い息を吐いた。ステラも思い出したように息をする。
ぶつかりあう額から、互いの熱と鼓動を感じた。
「やばいくらい、嬉しい・・・・・・です」
言ったかと思うと、シンの瞳はすぐに伏せられた。次いで乱暴なほどの勢いのキス。
顔が見たいのに、近すぎて見えない。ステラは勢いに押されてそのまま後ろに転がってしまう。いつもより乱暴なキスが上から落ちてきた。
驚いても離してくれず、何も言わせまいとするように塞がれた。
なんだか、ちょっとシンが怖い。戸惑うステラを待つ気配もなく、無言のままシンは顔中にキスした。
「シ、ン」
「ごめん。俺、突っ走ってるね」
シンは突然、腕を突っ張って体を起こすと途端に離れていってしまった。たくさんあった熱が急に去っていってしまってステラは寂しくなっ
た。気が付くと無意識にシンの腕を引っ張ってとめていた。
「シン、どこいくの」
ステラは急に起き上がれなくて、寝転がったまま問うた。どうしてシンが困った顔をして更に離れようとしているのかわからない。あんな
に近かったのに。
何かしただろうか。
「シン?どうして、後ろむくの」
「えー・・・・・・と、うん、いろいろあるんだよ。うん」
「いろいろ?」
シンは背中を向けたまま、動かない。
どうやら戻ってきてくれそうにないので、ステラは自力で起き上がって頑ななその背にもたれ掛った。
「あったかい」
心が温かくなる。無駄のない鍛えられた背中は少し肉が足りない感じがしたが、ステラはシンらしい骨っぽいこの背が好きだった。
「ステラー・・・」
「シン」
顔が見えたのが嬉しくて、ステラは笑顔になった。でもシンの方はやっぱり困った顔のままだった。それでもこっちを向いてくれた事が嬉し
くて、体の向きを変えてその背に抱きついてみた。
「もう、寝よう!遅いから!」
シンは急に立ち上がると、振り返ってステラを抱きかかえた。
「ほわ」
軽々と持ち上げて、シンは足早に隣の部屋に向かう。腕の中から見上げたシンの顔はやっぱり、困った顔のままだった。
『レイ、ステラに何をふきこんだわけ?』
携帯の向こうから聞こえてくる声はやけに不機嫌だ。レイは携帯を耳から離して、しばらく待った。
「気は済んだか?」
『聞いとけよ!』
こんな夜更けにと言いたかったが、シンには届きそうにない。小一時間、ずっと同じ話題をエンドレスである。
「シン、嬉しいだろう?お前が積極的にならないから、ステラに友人としてアドバイスしただけだ」
『なんて!』
「シンがほしいって言えば、もやもやはなくなるって言った」
『レーイー!!!』
耳からかなり離しても届く声でシンは叫んだ。
「ステラが起きるぞ」
『・・・・・・外だよ、俺は』
なんでまた。
『俺、何するかわかんねーもん・・・・・・』
ほう。
「シン、お前可愛いな」
『なんなんだ、お前はっ!』
いや、それは俺の台詞だ。シン・アスカ。今、何時だと思っている。
「お前こそ、どうしてステラにはそうなんだ?ルナマリアには早々に手をだ」
『黙りなさいよ』
「おかしいぞ、キャラが」
レイは思い切り溜息をついた。シンもレイも明日はまた任務である。寝不足で挑めるようなものではないのをレイはタリアから聞いて知って
いるだけに、どっと疲れた。
「大事にしてるのはわかったから、我慢してステラのところに戻ってやれ。風邪ひくぞ」
『・・・・・・寒くない。熱いぐらいだ』
「そうだったな」
『いちいちムカツクんだよ!他人事だと思って』
「他人事だ」
『ムカツクー!!』
女子高生みたいなことを言う友に、レイは苦笑した。しょんぼりしたり怒ったり、叫んだりと忙しない。
「ステラ、寂しがってるんじゃないか?」
『・・・・・・たぶん、待ってる』
なんと一途な。
「シン。最高のチャンスだろう」
『チャンスとかいうなー!っぶえっくしゅん!』
思わず、レイはまた物凄く遠くに携帯を離した。耳が割れそうだ。
「ほら、帰れ。明日は任務だぞ」
何か言いたげな間があいたが、シンは鼻をすすると漸くぶっきらぼうに言った。
『自信ないんだよ・・・・・・』
「何度も言うようだが、ステラは壊れたりしないぞ」
確かに彼女はまだ幼い。シンが自分をどう見ているか、理解してはいないだろう。だが、だからといって距離を置くことがステラにとっていい
ことのように思えなかった。
良くも悪くも、真っ直ぐで素直すぎるのだ。いらぬ誤解を招くような気がレイにはしていた。
「まあ、俺から助言できるとすれば、今夜はとにかく我慢しろ。無理なら、据え膳精神でいけ」
『なんか、お前、面倒になって適当いってない?』
「そんなところだ。じゃあな、おやすみ」
まだシンが何か言っていた気がしたが、レイはもう電源ボタンを押していた。これではきりがない。
ひとつ、顔を振ってレイは苦笑を浮かべた。
なんとも頼りない友でる。
戦場ではあんなに前のめりだったのに。
ステラ、君と俺はやっぱり似ているのかもしれない。
哀しい生い立ちも、この足掻きようも。
自分が何かも知らずに生まれ、その事実を知り、それでもなお「人」として生きたいと願ってしまう俺たちは、やっぱり「人」に助けられて支
えあって、生きている。
君を見ていると、こんな自分にもいつか叶うかもしれないと信じたくなる。
いつかの日、君に抱いたあの羨望の意味を俺も見つけることができる日が来るかもしれない。
そう、信じたくなる。
そんな日がもしきたら、真っ先に伝えよう。
黄金色のともだちに。
それから数時間後に出艦したレイは、明らかに眠っていないシンと遭遇することになる。
指輪はアスランに先を越され、告白もどうしてかステラに先を越され、自分だけが盛り上がってしまったことに苦しみながらも、まだ
指輪を渡せないでいる親友に、そっと手を合わせたのは言うまでもない。
黄金のともだち。完
おうおうおう。もう何もいうまい。
なんだか、うまく描ききれず・・・。くるしい。レイー。
また別でもっとレイとステラを会話させたいな。シンがヤキモチだな。
さあ、そろそろ指輪を渡させてあげなきゃシンが怒りますね。
頑張ります。